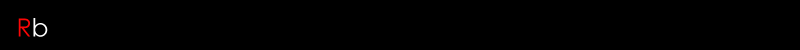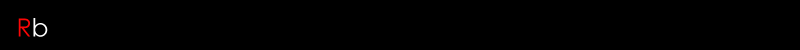Title: 「自分」と「なにか」
「自分」と「なにか」
そのなにかは、白紙の紙でも、季節でも、日本酒でも、人でも、時間でも、空気でも雨でも、それはなんでもいいのだけど。そのなにかと自分の間になにもない、なにも隔てない時にだけわき上がってくるものというのがあって、なんていうか余計な雑音もなく、「自分」と「なにか」だけになった時に自分の中で感じる事のできる感覚を持っているかどうかというのは、人と人がわかり合うときにとても大事なる。
その感覚はなんていうか、眉唾なものなどではなく、たとえばそれは、学校を休んで昼間に家の布団の中にもぐっている時のような感覚や、運動会の徒競走で負けたときの感覚や、富士山の頂上で日が昇るのを見た時の感覚とか、そういう類のもので、同じ所にいるときに同じように感じるであろう、とても感覚的なものだ。
その感覚の中にすとんと落ちたときに、自分となにかの境目がぼやけて、自分ではないその何かと自分がとけこむような感じ。その感じの中にいると、世界はどこまでも広く遠いのだけど、でもそれは間違いなくこの自分の手の中に繋がっているような気持ちがして、どこまでも言葉は言葉で、自分となにかを隔ててるこの身体すらも、またただの身体なのだなとすら感じる。
しばらくそこに浮かんでいて、ふとこの心地よさをずっと保ちたいなとか、捕まえておきたいなと思った瞬間に、それがかき消える。かき消えてはまたそこに出会って、出会ってはまたかき消える。
それを何度も何度も繰り返してきて、やっと最近すこし、その心地よさを自分の手の届くくらいのところにとどめておけるようになって、正確にはとどめているかどうかはわからないけど、離れてしまったときにはわかるようになってきたように思う。
なんかこう書くと、とても正気な人間の言葉とは思えないかもしれないけど、ようは、自分の取扱説明書がとても効率よく書けるようになってきたということかもしれない。
答えは一つもないとかいいながらも、その言葉は結局のところ一つの答えに帰着するんだきっと。
つまるところ、1も2も。3も4も。5も6も。春も夏も秋も冬も。雨の日も晴れの日も。好きも嫌いも。ぜんぶ一緒で。現実には匂いも色もなくて、色も匂いもないからこそどこまでも広く深く、自由で寛容で非情なんだ。
生きてる事とか現実を0だとして、そこには本当は匂いも色も影も形もない。ただの0で。
人が生きていくということは、そこに1や2やπや√をプラスして生きているのかもしれない。ある人は0+1+π+√かもしれない。ある人は0+5×35(2+1)かもしれない。
みんな自分なりの数式をくみ上げて、その中で共通項をみつけて、時に一緒にいる相手の数式に公約数をみつけたりしながら生きてるんだ。
でもそれは結局のところ計算上の話で、夢うつつみたいなもので、あくまで0になにかをプラスしているにすぎないんだなと。
その数式をうまく華麗にくみ上げることよりも、一つでもとっぱらって、0に近づいてみたい。そもそも数式は自分でくみ上げるというよりは、それはほっておいても周りが数字を当てはめてくみ上げられてしまったものにすぎないのだし。
ぶっこわして0に。0に。
それはきっと前に前にと同じ意味なのだと思う。
そんなことをおもいますた。
POSTED @ 2013.11.14 |
Comment (0) |
Trackback (0)