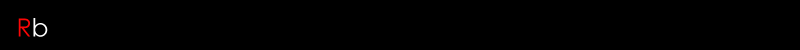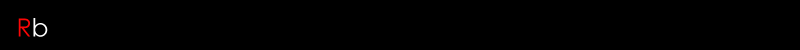Title: 叙情的な対となるどんぶりと自己。
小気味のいい湯切りの音に耳を澄ます。
単調でいて心地よいそのリズムに耳を澄ませていると、
それがまるで催眠術かのようにここではないどこかに誘われる。
それが味噌なのか、塩なのか、醤油なのか。またはそのどこにも属さないものなのか。
そんなことを考えるということはもはやここでは意味をもなさない。
それが" 何 "であるのか?
その問いに対する答えはどこかに存在するのだろうか。
目の前におかれた器の中から立ち上る湯気の向こうの景色がまるで蜃気楼のように揺らぐ。
湯切りをしていた男は、六十前後の小柄だが骨太な体躯をしていて決して人を寄せ付けないような雰囲気を漂わせている。
何が現実でなにが現実ではないのか、うつろとする意識の中で箸を割る。
乾いた音が店内にこだまする。
オアシスに飛び込むかのようにスープをすすりあげるとおもむろに麺を持ち上げた。
麺の上をスープが滴る。
その一滴が器の中に波紋をつくる。
その波紋が静けさとなって広がっていく。
昼下がりにラフマニノフを聞いているかのような涵養にただ身をゆだねる。
今、どんぶりと自分を隔てているものは何もない。
いやむしろその隔たりをつくっていたものはいつだって僕自身だったのかもしれない。
" こちら "と" あちら "の境界はいつだって突然に曖昧になる。
時折その感覚に頭の先から落ちそうになる、それは概念的にというだけではなく、
事実感覚的に落下していたのかもしれない。
やれやれ、何が言いたいかって、
そう、今無性に天一が食べたいんだ。
そして最近「騎士団長殺し」をどっぷり読んでいるということだ。
はい頭の体操終わり、仕事仕事。
POSTED @ 2017.02.28 |
Comment (0) |
Trackback (0)