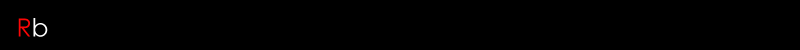




|
 Title: 対話。
先日祖父の書いた原稿をみつけた。こんな人が身近にいたのに、どうして生きているうちにもっと話を聞いておかなかったのだろうと思ったし、当時の自分にまだその時がきていなかったことがとても悔やまれた。 祖父の書いたものを読んで、そこに書いていることのどれだけが自分の中に落ちて、どれだけのことを受け取れたかわからないけど、今の自分に理解できたこと、腑に落ちたことだけでも、今の自分の言葉で書き下してまとめておこうと思う。 * いつの時代でも同じだと思うのだけど、人間の内心に生じる動揺や悩みを語り合うということはとても難しい事で、ときに人はそれを恥ずかしいと感じてしまう。
それにその心の動揺がなにによって生じたのか、なにが原因なのか、悩みそのものの内容が何であるのか、それを明らかにすることは、ときに人間として、自己の現実を突きつけられ、もしかすると目の覆いたくなるような、耐え難いようなみじめさと対面しなければならない。 それが耐え難いければ耐え難いこそ、そこに多くの曲折と、転嫁と、昇華を繰り返して生きていくことになる。しかしそれを繰り返すことで、本来の問題の所存すら見失って、結局のところ空転する解答に呻吟してしまうのではないだろうか。 そして、人間はそこで生じる感情を受け止めて、共感してくれる友をつねに探し求めているのだと思う。その友は誰でもいいというのではなく、無数の問いと解答の中に、移ろう心に答え得る友が欲しいのだ。 自分の周りには、群衆としての人間というのは無数にいるけど、その多くは自分とは無縁の存在だ。意識の表面に流れては去っていく幻のようなものだ。ともに酒を飲み交わし、仕事をして、はげましあい、笑いあい、泣き合っても、多くはお互いに人間であることを確かめ合うことはできない。 文明が進歩して、人間の視野は拡大して世界は縮小して、その視野によって捉え得る群衆の量は増大されたけど、果たしてじかに手を触れ体温をたしかめ得る人間が増えただろうか。 現代では時にあらゆる世界の人間とも心を通い、無数の同朋をもっているかのような錯覚に陥ってしまって、本来あるべき人間関係を軽視する。SNSなどがいい例なのかもしれない。そのことによってかえって無数の大衆からはじきだされているようにも感じる。現代ほど人に触れることを拒否して、心を許すことを拒絶している時代はないのではないかと感じる。孤独を孤独と感じることなく疎外されていることが既存設定になっているような。 神に対しても無感動である。人間に対しても不信である。すべてに対して麻痺された感覚が、虚無を底流として刺激を求めている。外面のはなやかさに比して、その底を流れるものはきわめて冷え冷えしたむなしさであることも少なくない。そのむなしさを正確にとらえているのが肉体だろう。自らの血を流すことも、性への執着も孤独な心そのものなんだろうと思う。それは肉体で人間であることを確認しようとする原始的な本能であり、自らが人間であることを主張しているのかもしれない。 それは、刺激に満ちたはなやかな「社会」にかいま見る人間主張の悲哀である。悲哀を内に秘めつつも、作為された「社会」に救いを求め続けなければならないというこのスパイラルが人には課せられているのだ。 何をしてもつまらない。何をしても本質的には退屈なのだ。そして孤独なのだ。それが人間を無感動にして、ドライにする。 思うに、現代の人がドライな生活スタイルをとるには、そうせざるを得ないからなのかもしれない。それは内心の動揺が生みだす絶妙なバランスを保つための手段であるように思う。それはどこかに比重がかかれば脆くも崩れ去ろうとするようなバランスである。 そのバランスが崩れるときに、それは問答無用に刹那的な行動となって無感動に人を殺すこともある反面、その衝動は無条件に涙を流させることもある。その涙を流す顔は、父を求め、母を求めてる幼い子どもの顔なのだ。この顔は10代の少年の中だけにあるのではなく、30代になっても、40代になっても、老人の中にさえもある。それはいわば、人間の体温を求めている顔だ。人間をとりもどしたときの顔だ。 だから、人は、この顔に出会うとホッとしながらも、どうしていいのかとまどうのだ。この顔を懐かしみつつも、その顔をどう受けとめていいのか困惑するのだ。ここに現代人の感傷と脆さが隠れているように思う。 簡単に善悪をきめ、簡単に善悪を放棄する。単純な価値観の設定だけに急かされて、内面的な思索が行われないのだ。すぐに頭にきて、衝動に身をまかせ、あとは無責任な感傷に涙を流す。その感傷はあくまで表面的で、深い世界まで結びついていないのだ。 それは生活の多様性が意識の分散させ、思考の転換を要求するために、思いつめて物を考える習慣をうばい去った結果である。機械的に物事を判断して、機械的に行動する、それは多様性に対応するためのテンポの早さを生活の中で常に要求されるからだ。 「社会人」に最も要求されるものは、適応力だ。それには敏捷な価値判断とそれに基づく行動力が必要なのだ。だから、人物評価も、学歴、特技といった生活能力に表され、いわば敵か味方か、善人か悪人かという、用意されたレッテルによって色分けされる単純化が行われる。そうしなければスピード感を失うからだ。 しかしそれは人間不在で、いわば冷酷な単純化でもあると感じる。その単純化された中で、今年の景気は、世界の情勢は、今年の流行はと、時代や経済や流行に敏感に触角をとぎすまして刹那的に適応化が行われているのだ。 その適応性に裏付けされて、生活は高められたというが、高められたものは、生活の様式、あるいは生活の技術といったものである。もちろんそこにはそれなりの生活の喜びもある。しかしながらいつまでたっても近代生活の根底に、多忙を抱えながらも、退屈を覚えて、むなしさを感ずるのはいったいどういうことなのか。 最近仏教に関心が高いという若い人が増えたように思う。しかしこれは決して意外なことなのではなく、あるいは当然のことのように思う。つまりはこれこそが、「生活」の陰にかくれた、人間回復の願いのようなものなのかもしれない。 生活様式がどう変わろうと、人間が人間であることに変わりはないのだ。人間とは何か、ほんとうの幸福とは何か、真実の喜びとは何か、こうした問いが、多様な生活の中で問い続けられている。つまりは生活とはこうした二面性を持っているのだろう。 一面では、生活様式の合理化を技術的に追求しながらも、一面において、人間の存在の本質を問い続けているのが人間というものである。 「生」とは、生きることであり、生まれてくるということである。永劫の生命の流れの中に現に生まれて、限られた命で生きているのである。死は必然にしのびよってくる。そこに無限な延長はない。その限られた生命をいかすのが「活」なのではないだろうか。「活」の中には、限られた生命の充実が切実に願われていて、無常ゆえに、限られた生命の安全を願い、有限なるがゆえに、限られた肉体の快楽を願うのだ。 「活」は無常をはらみつつ、無常の忘却を願うものだろう。生まれおちたこの人間の存在をあるがままに、いかに主体的に受けとめるかであり、無常にさらされて、有限の肉体をいかに生きぬくか、これが生活をすることの根底にある苦悩なのだ。 その苦悩の中で、「愛欲の広海に沈没し、名利の大山に迷惑する」ものが迷情の「活」なのだ。「真証の証に近づくことを快しまざるを、恥づべし傷むべし」というのが「生」なのだ。 社会的な名誉や、地位や、お金は、身を守るために最も必要なものだ。人間はその名誉や利益という名利によって永遠を幻想し、身の安全の上に、生命の燃焼を欲望する。それは歴史上何人も願ってやまないところである。しかし、それをして沈没といわせ、迷惑といわしめる何か人間の中にはがうずいているのだ。 その「活」の根底に深い問いを投げかけてくるものこそが「生」ではないだろうか。それは聖人が750年前に悲嘆した世界も現代においてもなんら変わりもなく。 昔の人は単純であったというが、単純だったのは生活様式であって、生活そのものではない。過去の時代において生きた人間も、それぞれにその当時の現代を生きているのである。人間はつねに「今」ここに生きている。昔は単純で、現代は複雑である、だから昔の人間の祈りは幼稚であったということは決してできない。 中には幼稚な迷信に翻弄された過去もあるかもしれないし、現代に多くの迷信もあるけれど、様々な生活様式の変遷の中で願われてきた願いそのものの本質はなんら変わらない。 真実を求める求道の心に過去はない。祈りの響きに過去というものはあり得ない。無限の解答を求め、無限の解答を産み出し、その解答に流されつつも、問い続ける問に過去というものはありえない。 その生きた心において問いを発し続けているのが人間だ。 解答は過去に押し流されることはあっても、問いそのものは、常に現在において問われている。解答は過去に押し流される宿命なのかもしれないけれど、産み出す問いそのものは、常に「今」であり「現在」なのだ。 人間は、いつだって現在において問いを発していて、その問いの歴史をたずねるものこそ、宗教というものなのかもしれない。その問いの世界を明らかにするものが仏法であって、仏法とは、問いの中にあって問いそのものの世界を明らかに聞き開くことなのだ。 まえにまえに。 |
 

|
